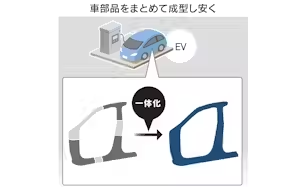製造は1社のみの“絶滅危惧”酒
伊勢神宮の最も重要な祭祀である三節祭(10月の神嘗=かんなめ=祭と6月、12月の月次祭)には醴酒(れいしゅ)、白酒(しろき)、黒酒(くろき)、清酒の4酒の酒が奉納される。それらは清酒を除き、神域内にある忌火屋殿(いみびやでん)で古式にのっとって醸造される。醴酒は甘酒。白酒は白く濁ったどぶろくのような酒をざるで濾したもの。これに草木灰を加えたものが黒酒である。
この黒酒から名前を取って商標にしたのが東(ひがし)酒造の「黒酒」で、こちらは「くろざけ」と読む。私がこの黒酒の存在を知ったのは1年ほど前、さつま揚げの取材で鹿児島を訪ねた時のことだった。
鹿児島土産の代表であるさつま揚げは、白身魚や青魚のすり身を原料に塩、砂糖、アミノ酸系調味料などで調味し、成形して揚げたものだが、多くの製造元がみりんか「地酒」と呼ばれる料理酒を使っていた。
この「地酒」の正体を探るべく、改めて鹿児島に向かった。
「地酒というのが一般名詞で、当社の製品の商品名が黒酒になります」と、東酒造4代目社長の福元文雄さんが教えてくれた(地元の酒を示す「地酒」と紛らわしいので要注意)。以下は福元さんによる「地酒概論」である──。

東酒造の福元文雄さん 写真:浮田泰幸
現在、ほとんどすべての日本酒は火入れ(加熱処理)によって保存性を高める「火持酒(ひもちざけ)」である。この製法は江戸時代に始められたもの。これに対し、少なくとも1200年前の平安時代から灰汁(あく)を用いて保存性を高める「灰持酒(あくもちざけ)」という製法があり、この流れを汲むのが鹿児島の地酒である。冒頭で述べたように、神事に欠かせない灰持酒を九州では正月のお屠蘇(とそ)として飲む風習があり、日常的に愛飲する人もいるが、現在の利用はほとんどが料理用である。
ほとんど精白しない米(酒米ではなく、食用米)を原料としているので、各種アミノ酸が多く含まれ、うま味に富む。また火入れをしないため、酵素が失活することがないことも大きな特徴である。酵素とアルコールの働きにより、肉や魚の臭みを消し、肉質を柔らかくし、味の浸透を良くし、風味を引き立てる。用途的には本みりんと重なるが、もち米と米麹(こうじ)を米焼酎に漬け込んで造る本みりんはアルコール発酵の工程を経ないので、酵素や有機酸を含まない点で地酒と異なる。
江戸時代には鹿児島県内でも多くの酒蔵が地酒を造っていたが、焼酎造りが盛んになるとともに衰退してしまった。現在、灰持酒の伝統は、鹿児島の他、熊本(赤酒)や島根(地伝酒)に残っているが、3県すべてを合わせても生産者の数は10軒に満たない。火入れをまったく行わないものは東酒造の黒酒のみであるとのこと(東酒造調べ)。いわば“絶滅危機食品”だ。実際、第二次大戦後に原料である米の供給が止まり、製造が途絶えてしまった時期があった。それを復活させたのが同社の創業者、東喜内(ひがし・きない)氏だった。1955(昭和30)年のことである。
当時は「高砂の峰」という商品名で、金色の地に赤い盃が映えるクラシカルなラベルだった。地元の人には今もこのイメージが親しまれているという(「高砂の峰」は間もなく終売になる予定)。1990(平成2)年、これを改良、原料米の量を増やし、アミノ酸値を倍増し、業務向けに開発したのが黒酒である。
18種類ものアミノ酸が生み出す重層的なうま味
黒酒の製造工程は、途中までは一般的な清酒の場合と同じである。黄麹と蒸米で米麹を作り、それに酵母と乳酸と水を加えて酒母を造る。三段仕込みでもろみを作り、圴一な発酵を促す。発酵が終わると灰汁を加え(ここが灰持酒たるゆえん)、搾り、醸造用アルコールと糖分を添加して規定の品質にする。

蒸し上がった米と(左)、蒸米の温度をチェックする蔵人(右)。季節やその日の天候で微妙に最適な温度が異なる 写真:浮田泰幸

桶に原料を投入して撹拌する工程 写真:浮田泰幸

発酵が始まったもろみ 写真:浮田泰幸
使われる麹が黄麹であることに注目したい。黄麹は主に日本酒造りに使われる麹だが、暑さに弱く、十分なクエン酸を出せなくなることから元来九州での酒造り/焼酎造りには不向きだった。それで20世紀前半に研究・培養されたのが現在の焼酎造りで使われている黒麹や白麹だった。東酒造では古来の製法を守るべく黄麹を用いているが、醸造所内の室温をエアコンで管理してリスクを回避している。「地酒の生産が減っていった背後には、温暖化が進んだこともあると思います」と福元さんは言う。
東酒造は灰持酒の製造に欠かせない木灰を自社で作るための設備を南さつま市に有する。樫の間伐材を3時間かけて燃やし、できた木灰に水を加えたものを濾して灰汁を作る。灰汁は、見た目は何の変哲もない無色透明の液体だが、強アリカリ性であるため取り扱いには注意を要する。

樫の木の間伐材を焼いているところ 写真:東酒造

灰汁。強アルカリ性の灰汁でpHを上げることで酒の保存性を高める 写真:浮田泰幸
黒酒をテイスティングしてみよう。色合いは糖とアミノ酸が反応して起こるメーラード反応により淡い飴色を呈する。アルコール分は13.5~14.5度。デーツのような甘苦い香りに穀類の皮、ドライフラワーや干草、薬草の香りが混じる。口に含むと、トロリとした粘性があり、丸い甘味、複雑かつ強烈なうま味があり、後口に軽い苦味が残る。

(左)1300年の歴史がある灰持酒の特性を継承した黒酒(右)先行商品の高砂の峰 写真:浮田泰幸
「鹿児島大学水産学部の加藤早苗准教授らと共同で黒酒の成分分析等の研究を行っています」と福元さん。その結果、黒酒には18種類に上るアミノ酸が含まれることが分かった。うま味成分の代表格として知られるグルタミン酸だけでなく、多くのアミノ酸が共存することで、複雑で奥深い味がする。市販の本みりんと比べ、アミノ酸の含有量は2倍以上。また糖度は本みりんの6割程度だが、多様な糖類から成るため、甘みがマイルドで深みがあることもわかった。
黒酒自体の味や香りが調味に役立つだけでなく、すでに述べたように酵素とアルコールの力による副次的な効果が期待できる。主役ではなくスーパーサブになれるということだ。さつま揚げの製造を例に取れば、黒酒によって揚げ色、弾力、舌触りが向上、好ましい香りを付加することが分かっている。
つまり、和食のレシピの定番である「酒とみりんとしょうゆを1:1:1で」の調味が「黒酒としょうゆ」で済むことになる。しかも、出来上がりは後者の方がベターとなれば、みりんの存在は危ういと言わざるを得まい。
作りたてのカレーが「2日目」の味に
現在、黒酒は主に業務用として流通している。多くのさつま揚げ工場で使われている他、そば店(ゆでたそばを締める冷水に黒酒を混ぜて利用)、明太子業者(調味液に)、餃子店(あんに)、水産加工業者(干物の下処理に)等々に出荷。

揚げたてのさつま揚げ(上揚げ)。黒酒は食感や揚げ色もよくする 写真:浮田泰幸

さつま揚げの工場で魚のすり身に黒酒を投入するところ 写真:浮田泰幸

田中蒲鉾店の田中健太さん(右)と直子さん。先代の時代から黒酒を使っている 写真:浮田泰幸

鹿児島市内の「吹上庵」のそばは、ゆでた麺を冷やす水に黒酒を入れている。そうすることでそばの風味がボケないとのこと 写真:浮田泰幸
東京・銀座にあるミシュラン2つ星の寿司屋「鮨よしたけ」の主人・吉武正博さんも愛用者の一人。以前、出演したテレビ番組でアナゴの下処理の際に黒酒を噴霧していることを公表し、「これを吹きかけることによって、細胞の中に酵素が入ってふわっと膨らむ」と述べている。
取材後、私も黒酒を入手して、実際に台所であれこれ試してみた。下ごしらえよりは調味料として使ったが、煮物や汁物はこれを入れることで味全体にまとまりが出る。驚いたのは、作りたてのカレーに黒酒を入れると「2日目のカレー」のような味になったことだ。福元社長が話していたように、少量で効果があり、料理が冷めても風味が萎(しお)れないことも実証済みである。
天然素材を用いていること、伝統手法で造っていること、「うま味」や「酵素」がキーワードであること、どれを取っても現代の食のトレンドと合致していて良いことずくめだ。黒酒の存在はもっと知られても良いのではないかと思う。国内の一般家庭でも、そして海外でも。
最後に福元さんが教えてくれた興味深いエピソードを添えておこう。灰持酒を復活させた東酒造創業者・東喜内氏は100歳まで現役で活躍、102歳の長寿を全うしたそうだ。

噴煙を上げる桜島。黒潮の流れに乗って伝播した発酵文化と風土が地酒を生み出した 写真:浮田泰幸
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。